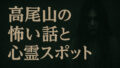年間約300万人が訪れ、「世界一登山者数の多い山」として知られる高尾山。ミシュラン三つ星の評価を受け、2020年には「日本遺産」にも認定されました。夏には「清涼体感めぐり」などのイベントが催され、多くの家族連れや若者で賑わいます。
しかし、その華やかで平和な顔のすぐ裏側に、私たちが普段目にすることのない、もう一つの物語が静かに息づいていることをご存知でしょうか。
終戦から80年の節目を迎えようとする今、多くの人が行き交う日常の風景に刻まれた「戦争の記憶」に、少しだけ耳を傾けてみませんか。

そこには、遠い昔に亡くなった人々の声と、現代に生きる私たちへの静かな問いかけが聞こえてくるはずです。
日常の風景に刻まれた戦争の記憶 – 高尾駅ホームの弾痕
JR高尾駅の1番線・2番線ホーム。多くの乗降客が足早に行き交うその場所に、異質な存在感を放つ鉄柱があります。屋根を支える柱には、生々しい「弾痕」が残されています。


これは、今から約80年前の1945年7月8日、米海軍の艦載機による機銃掃射で刻まれた傷跡です。当時「浅川駅」と呼ばれていたこの駅は、軍事輸送の結節点でもあったため、攻撃の標的となったのです。
この鉄柱が持つ歴史はさらに深く、柱そのものが日本の近代化を象徴する遺物でもあります。使用されているレールは、1902年(明治35年)に官営八幡製鐵所で製造された、現存が確認されている中では国産最古級のものなのです。
一つの鉄柱に刻まれた、明治の産業振興、戦時下の物資再利用、そして戦争による破壊の痕跡。それは、日本の近代史そのものを体現する、沈黙の証人と言えるでしょう。
絶望のトンネル – 満員列車を襲った「いのはなトンネル銃撃事件」




高尾の戦争の悲劇は、駅だけにとどまりませんでした。終戦直前の1945年8月5日、この地で日本の鉄道史上最悪の列車襲撃事件の一つが起こります。
その3日前の8月2日、八王子市は大規模な空襲を受け、市街地の8割が焼失、多くの市民が犠牲となりました。街が恐怖に包まれる中、人々は一刻も早くこの地を離れようと、避難列車に殺到しました。
8月5日、そうした避難民や疎開者で満員になった新宿発長野行きの普通列車が、高尾駅を出発し「いのはなトンネル」に差し掛かった時、米軍のP-51マスタング戦闘機に発見されました。戦闘機は列車に執拗な機銃掃射を繰り返し、車内は阿鼻叫喚の地獄絵図と化しました。公式な記録でも死者約52名、重軽傷者約133名という甚大な被害を出したこの事件は、近代戦争の「致死的な悪循環」を物語っています。
- 都市への戦略爆撃(八王子大空襲)が、避難民の大量発生を引き起こす。
- その避難民が利用する交通手段(列車)が、新たな攻撃目標となる。
これにより、民間人の犠牲が連鎖的に増幅していくのです。現在、事件現場の近くには慰霊碑が建立され、「いのはなトンネル列車銃撃遭難者慰霊の会」によって毎年慰霊祭が執り行われています。
小さな背中に託された悲しみ – 「ランドセル地蔵」の物語
戦争の暴力は、軍事目標と民間人の区別なく襲いかかりました。その悲劇を象徴するのが、相即寺(そうそくじ)に佇む「ランドセル地蔵」です。




高尾駅が機銃掃射を受けたのと同じ1945年7月8日、都心からの空襲を避けて八王子に集団疎開していた9歳の少年、神尾明治君がP-51戦闘機の攻撃により命を落としました。息子の悲報を聞き駆けつけた母親は、悲しみの中、お寺の地蔵菩薩像が亡き息子の面影に似ていることに気づきます。そして、息子が大切にしていたランドセルをその地蔵の背中に背負わせ、供養したのです。
この母の深い愛情と追悼の行為から、「ランドセル地蔵」の物語は始まりました。戦争が最も無防備な子供たちの命さえも奪い去ったという事実を、この小さなお地蔵様は静かに、しかし力強く現代に伝えています。
悲劇の背景 – 秘密兵器工場「浅川地下壕」
なぜ、のどかな高尾の地が集中的な攻撃を受けたのでしょうか。その背景には、駅の南方に掘られた巨大な秘密軍事産業施設「浅川地下工場(浅川地下壕)」の存在がありました。
▼八王子市民活動支援センター 「平和への願いを込めて語り継ぐ「浅川地下壕見学会」記録動画」
重要な戦争生産拠点を空襲から守るため、中島飛行機(現在の株式会社SUBARUの前身)の航空機エンジン工場を疎開させる国家的なプロジェクトでした。総延長10km以上にも及ぶトンネル網の建設には、多くの朝鮮人労働者や学生らが動員され、過酷な労働に従事しました。
しかし、この必死の努力は、結局のところ非効率な結果に終わります。むしろ、この地下工場とそれを支える鉄道インフラの存在が、地域全体を格好の軍事目標へと変えてしまったのです。国を守るための地下要塞化という防御策が、地上に新たな悲劇を招く一因となったという、戦争が持つ痛ましい皮肉がここにあります。
80年の時を超えて – 「負の遺産」が私たちに語りかけるもの
高尾に残るこれらの戦争の傷跡は、苦しみや悲しみの記憶が刻まれた場所を、忘却から守り、未来への教訓として活用する「負の遺産」です。
| 遺跡名 | 歴史的重要性 | 現在の状況 |
|---|---|---|
| JR高尾駅の弾痕 | 1945年7月8日の機銃掃射の痕跡 | 原型の柱が案内板と共に保存されている |
| いのはなトンネル慰霊碑 | 1945年8月5日の列車銃撃事件の現場 | 慰霊碑が建立され、毎年8月5日に慰霊祭が開催される |
| ランドセル地蔵 | 疎開学童の死を追悼する地蔵 | 地蔵とランドセルが保存され、命日に特別開帳が行われる |
| 浅川地下工場(地下壕) | 中島飛行機の秘密地下工場 | 市民団体により保存活動が行われ、ガイドツアーで見学可能 |
これらは単なる古い傷跡ではありません。地域の人々や関係機関が、歴史を忘れないという強い意志をもって保存してきた「記憶の装置」なのです。
悲劇の先にある祈り – 国際友好の証「仏舎利塔」
しかし、高尾山が持つ物語は戦争の悲劇だけではありません。この山には、悲劇を乗り越え、平和への祈りが込められた場所も存在します。それが、男坂と女坂の合流地点近くに佇む「高尾山仏舎利塔」です。

この白い仏塔は、1930年頃にボーイスカウト日本連盟の代表団がタイ王国(当時シャム)を訪れた際に、タイのラーマ7世国王から特別に仏舎利(釈迦の遺骨)を寄贈されたことがきっかけで、1956年に建立されました。日本の青年たちの真摯な信仰心に感動した国王が、国境を越えた友好の証として贈った貴重な仏舎利が納められています。
戦争の記憶が刻まれた同じ山に、国境を越えた友好と平和への願いの象徴が静かに建っている。この事実は、私たちに希望を与えてくれます。高尾山は、戦争の悲劇を後世に伝えながらも、同時に国際的な絆と平和を希求する祈りの場でもあるのです。
まとめ – 終戦記念日に、足元の歴史を見つめ直す
私たちにとって身近な観光地である高尾山。しかしその一枚下の層には、戦争の悲劇、市井の人々の苦しみ、そして平和への切実な祈りという、深く重い歴史が横たわっています。
駅のホームの弾痕も、慰霊碑も、お地蔵様も、何も語りかけてはきません。しかし、私たちがその歴史を知り、足を止め、静かに思いを馳せるとき、それらは初めて「沈黙の語り部」となります。
終戦記念日を迎えるこの夏、高尾山を訪れてみてはいかがでしょうか。あるいは、あなたの暮らす町の片隅にも、きっとまだ語られていない戦争の記憶が眠っているはずです。

遠い過去の出来事としてではなく、私たちの日常と地続きの物語として戦争を捉え、亡くなった方々に思いを馳せる。それこそが、平和の尊さを自らの足元から見つめ直し、未来へと繋いでいくための、はじめの一歩なのかもしれません。
※最新の慰霊祭開催状況や見学会については、各関係機関にご確認ください。